
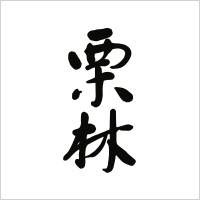
明治7年(1874年)秋田県六郷村(現美郷町)にて、栗林家5代目・栗林直治によって創業されました。 かつての六郷は佐竹公の隠居の地で、商業の中心地でした。仙北平野の良質の米と豊富な地下水に恵まれ、以前は酒蔵が20以上あったとされる地域です。 春霞の銘柄はいつごろから使われたのか定かでありませんが、謡曲「羽衣」の一節、「春霞たなびきにけり 久方の月の桂の花や咲く〜」から取ったといわれています。 また「霞」が古くは酒の異名であったことにも関係があるとされます。
清水の郷・秋田県美郷町。町内に126カ所もの湧水が確認され、名水百選(環境庁)にも選定された水の町。 奥羽山脈のふもと、扇状地の上にあるため地下水が豊富で、各家庭でも地下水を汲み上げて使用するのが一般的です。 蔵で使用している仕込水も、地下25メートルから汲み上げた地下水。その水温は年間を通して約12度前後で、水質は軟水。 一説には「酒を造るにはよく湧く軟水が良い」といわれてます。
昭和44年(1969)からは地元六郷出身の亀山精司氏が杜氏を務めました。 昭和50年頃より純米酒の製造を開始、全国清酒鑑評会で昭和60年に金賞を初受賞、以降は7度の受賞を重ねました。 この時期の、協会9号系酵母での酒造りは、現在の酒造りの基礎のひとつとなっています。 平成20年(2008)亀山杜氏の引退後は、代表社員(製造責任者)の栗林直章氏が酒造りを行っております。 現在は蔵付酵母「亀山酵母」と「熊本酵母」を使い分け酒造りをしています。
直章氏の代になった頃はまだ普通酒の割合の方が多く、当時の出荷の7割が地元でしたが、現在は県外が7割と逆転しています。 造りは年間で約600石と、人気であるNEXT5の蔵元というイメージからは決して多くはなく、身の丈で出来る限りのお酒を仕込んでいます。 そして2018年度より醸造用アルコール添加は仕込まず、全量純米酒になりました。また火入も全量手間のかかる瓶燗で行われています。
田んぼ違いの銘柄「栗林(りつりん)」に代表される地元の酒米「美郷錦」にこだわり酒造りをしています。 「美郷錦」は「山田錦」に「美山錦」を交配して育成され、2002年に登録された秋田県産の酒造好適米です。 性質的には「美山錦」に近い部分があり、「山田錦」などと比べると扱いも難しく複雑な味わいがありますが、 そのような部分も含めて「美郷錦」の面白いころでとあり、蔵の個性が出せると考えているようです。 現在造られるお酒の7割がこの「美郷錦」を使用しています。
-
#限定商品 #4月8日入荷
【日本酒】春霞(はるかすみ)純米吟醸【六号酵母】生 1800ml ※クール便発送
¥3,300(税込)
-
#限定商品 #3/15入荷
【日本酒】栗林(りつりん)純米【生・ピンク】六郷東根 2024 720ml ※クール便発送
¥1,595(税込)
-
#限定商品 #3/15入荷
【日本酒】栗林(りつりん)純米【生・ピンク】六郷東根 2024 1800ml ※クール便発送
¥3,135(税込)
-
#限定商品 #3/15入荷
【日本酒】栗林(りつりん)純米【生・クリーム】金沢西根 2024 720ml ※クール便発送
¥1,595(税込)
-
#限定商品 #3/15入荷
【日本酒】栗林(りつりん)純米【生・クリーム】金沢西根 2024 1800ml ※クール便発送
¥3,135(税込)
-
#限定商品 #2/28入荷
【日本酒】春霞(はるかすみ)純米吟醸【生酒】緑ラベル R5BY 1800ml ※クール便発送
¥3,630(税込)
-
#季節限定 #12/5入荷
【日本酒/新酒】春霞(はるかすみ)純米 赤ラベル【直汲み生】R5BY 1800ml ※クール便発送
¥2,970(税込)
-
#限定商品
【日本酒】栗林(りつりん)純米【火入・クリーム】金沢西根 2023 1800ml ※クール便発送
¥3,135(税込)
-
#通年商品
¥1,540(税込)
-
#通年商品
【日本酒】春霞(はるかすみ)純米 赤ラベル 火入1800ml
¥2,970(税込)
-
#通年商品
【日本酒】春霞(はるかすみ) 純米吟醸 緑ラベル 火入 1800ml
¥3,630(税込)
(全11件)11件表示
- 1










